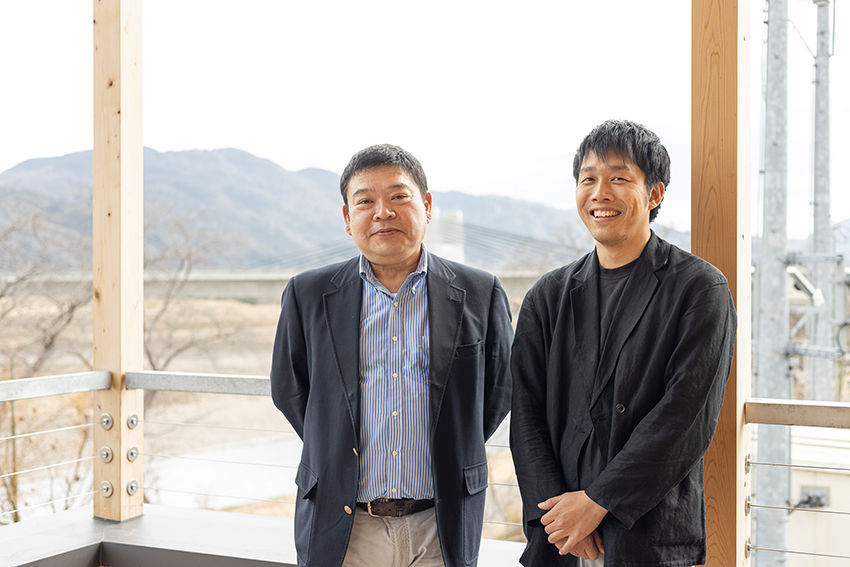特別対談 再生事業の進化を紐解く
日立建機が「再生事業」に込める思いは、これからの社会にどのような意義をもたらすのか―
「ごみの学校」を主宰し、廃棄物問題の啓発活動に取り組む寺井正幸氏(写真右)と、再生事業部長の菅原道雄。
異なる立場から環境問題に向き合う二人の対談から見えてきた共通点とは。
寺井:日立建機は再生の取り組みを1960年代にスタートしたと聞きました。廃棄物処理法が1970年に成立し、「燃やして埋める」がやっと始まった時代の前ですから、相当早い取り組みだったと思います。最近こそサーキュラーエコノミーの視点で中古車や中古家電も注目されていますが、当時はきっと新品の方がいいという時代ですよね。
菅原:きっかけは、高品質の製品を安価に手に入れたい、機械の休車時間を減らしたいというお客さまのニーズに応えるために始まったと聞いています。その後、社会環境が変化する中で廃棄への規制が増え、環境への意識も高まり、結果的に社会やお客さまとともに進化してきた事業だと実感しています。
寺井:社会の変化でお客さまの課題も変わり、環境の視点から再生部品を選ぶケースが増えてきたということですか。
菅原:そうですね。徐々にですが増えていますし、当社としても世界各地のグループ会社と協力し部品再生拠点を整備するなど、循環型社会の実現をめざす取り組みを強化しています。
寺井:新興国の環境規制が厳しくなり、これまでのように中古車を海外に売って、代わりに新車を購入する、というのは難しくなってきました。それなら部品を回収してもらい、再生部品に交換しながら少しでも長く使っていく方が、きっとメリットも大きいのでしょうね。
菅原:まさしくその通りで、例えば、これまでは5年で買い替えていたところ、メーカーがサポートするのであれば10年、あるいは15年と長く使っていった方がいい、と考えるお客さまが増えてきています。
ボトムアップの“ワクワク”がベース
寺井:とはいえ、こうした事業はトップダウンで動きがちで、社内の理解や協力を得るまでに時間が掛かりますよね。「ごみの学校」では、さまざまなモノをボランティアが無償修理する「リペアカフェ」の取り組みをしているのですが、その中で再生を事業として考えると難しいという話をよく聞きます。どういった姿勢で取り組みを進めていったのですか。
菅原:いま振り返ると、「ビジネスになるのか」とよく言われました。まずはとにかくやってみて、トライアンドエラーを重ねながら進めてきました。おそらく、お客さまのご要望に応えるという姿勢が根付いていたからこそ、社内の理解を得られやすかったのかもしれません。
寺井:なるほど。やってみないと何も進みませんし、とりわけ再生の事業はそうですよね。そこは本当に共感します。個人的には、KPI(重要業績評価指標)とサーキュラーエコノミーは相性が悪いと思っています。もちろん、ビジネスにおいては目先の指標も重要ですが、それより、長く付き合ってくれるお客さまが10社増えれば、長い目で見て売上につながっていく。そういったベクトルの方が向いているのではないでしょうか。
菅原:そうですね。当社では、お客さまのさまざまなニーズにお応えするため、新車販売だけでなく、部品・サービス、レンタル、中古車など、機械のライフサイクル全体をカバーする事業を展開しています。その中でも再生事業は、環境負荷を低減しながらお客さまと長期的な接点がもてる取り組みだと思っています。「ごみの学校」のコンセプトは「ごみを通してワクワクする社会をつくろう」ですが、私自身も同じ思いで取り組んでいます。実は当社のサーキュラーエコノミーの考え方は、再生事業部の若手社員の提案がベースになっていて、それを事業部で整理し、経営幹部に直接説明しました。それが会社としてサーキュラーエコノミーを打ち出すきっかけにもなったんです。
寺井:経営やサステナビリティ推進組織が起点で啓発活動を行い、事業部での理解を進めるという流れはよく聞きますが、ボトムアップで出てきたのはすごいですね。

「ごみの学校」運営代表
寺井 正幸氏
京都府亀岡市生まれ。大学卒業後、産業廃棄物処理業者に入社。産業廃棄物に関するセミナーや講演に50回以上登壇。現在は「ごみの学校」を運営し「ごみを通してワクワクする社会をつくること」を目標に活動している。
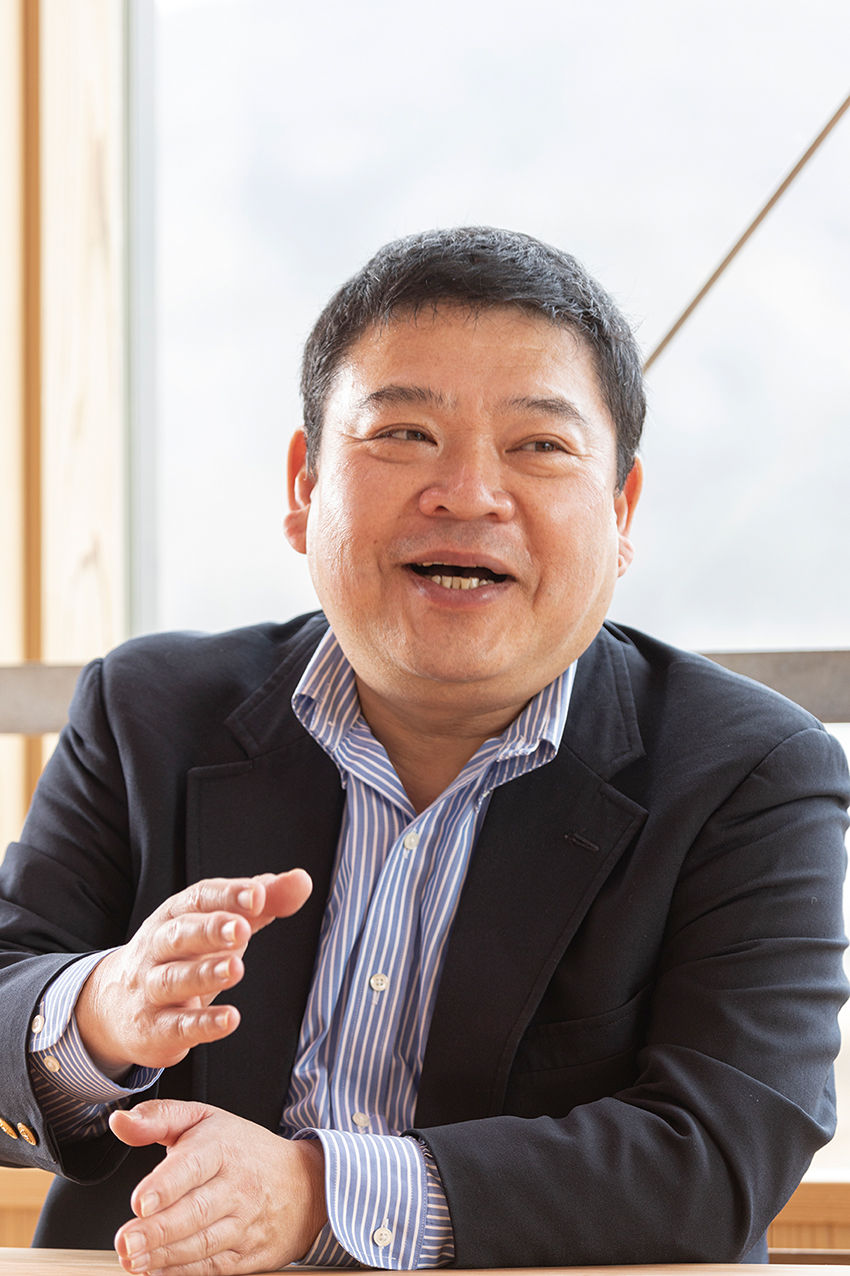
日立建機 再生事業部長
菅原 道雄
仲間と一緒になって取り組みたい
寺井:「ごみの学校」で活動する立場としては、本来、日本のメーカーは“100年使えるもの”を作るのがお家芸で、サーキュラーエコノミーに向いていると感じています。つまりこれからの時代、日本の勝ち筋がそこにあると考えているわけですが、海外発信のカタカナ語として出てくると、途端に自分たちには遠いものと捉えてしまう。むしろそれは祖業、本業に近しい価値観だと気付いてほしいですね。
菅原:日本は資源が限られた国ですから、大量生産・大量販売・大量消費のビジネスモデルはなじまず、資源循環の方法論を取り入れないと企業としても生き残れない、と私も思います。
寺井:おもしろいことに、リペアカフェに持ち込まれるものも、最近の製品は意外と直せません。やはり昔のものは修理して使える構造になっているんですね。消費者の意識も変わってきていると思っています。私が運営している「ごみの学校」も、そういう意識を共有できる仲間たちの集まりから広がっていきました。とりわけ若い世代は環境貢献やシェアの考え方に共感しますから、日立建機の再生事業というビジネスモデルがもっと広まり、日本企業が本来持っている良さに気付いて、同じようにチャレンジしたいと考える仲間がどんどん増えてくればいいと感じました。
菅原:いま、再生事業に一緒に取り組む仲間づくりをしています。やはり仲間が増えれば楽しいですし、その先で事業が拡大すると達成感やうれしさもあります。そうした“ワクワク”を大切に、再生事業でお客さまに提供するサービスのさらなる改善と、いっそうの環境貢献に取り組んでいきたいと考えています。
文/斉藤 俊明 写真/那須 亮太