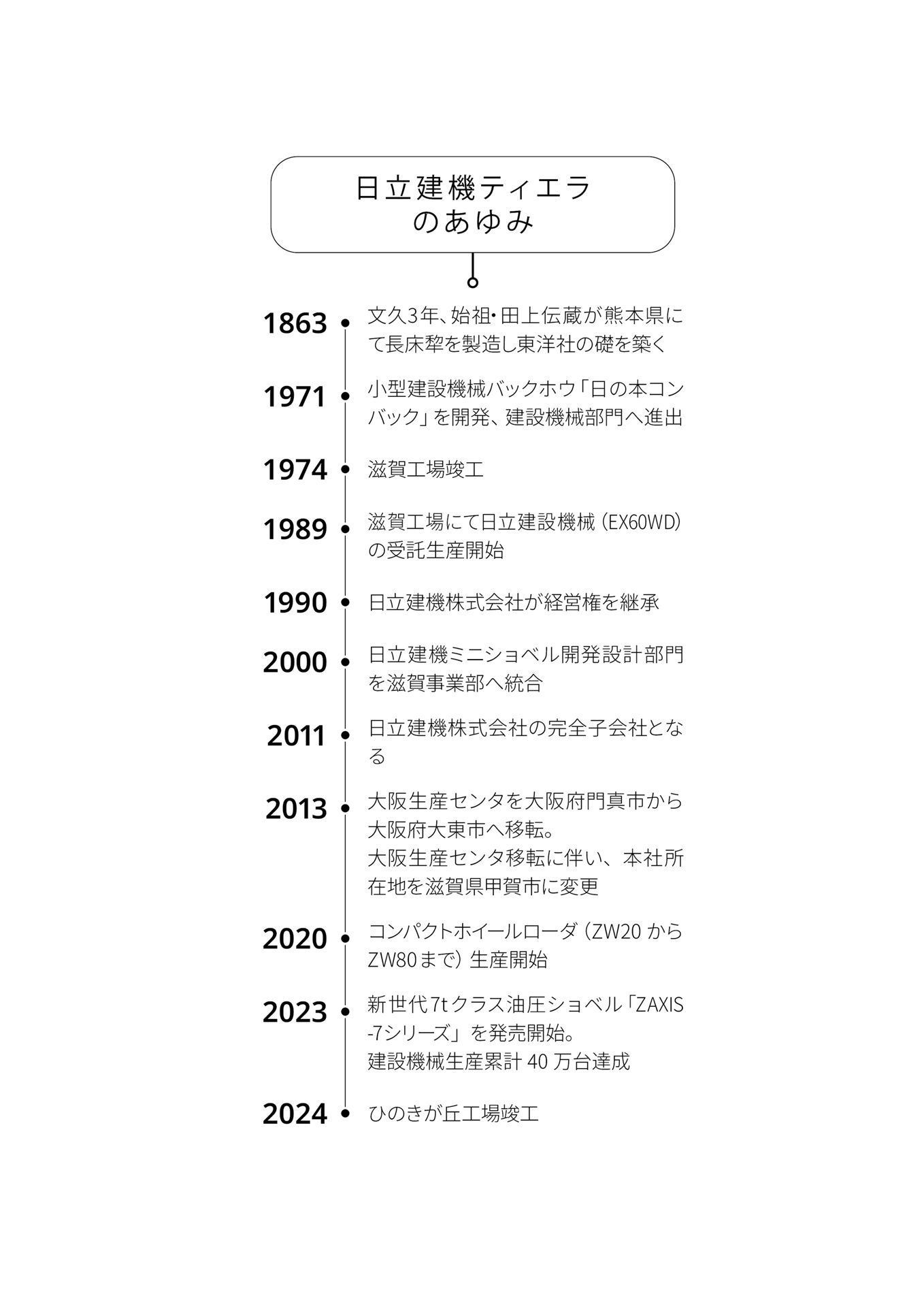小さな建機、大きな可能性

狭所での土木工事、家屋の解体のほか、除雪や農林業・畜産、造園など幅広い分野で活躍するコンパクトな建設機械。
コロナ禍後の景気回復や都市化の進行などが追い風となって、世界的にコンパクトな建設機械市場の拡大が顕著だ。
また、欧州を中心に環境配慮型製品への期待も高まっている。
そうしたニーズにこたえるため、日立建機ティエラはコンパクト製品の生産性向上や開発環境の高度化に取り組んでいる。
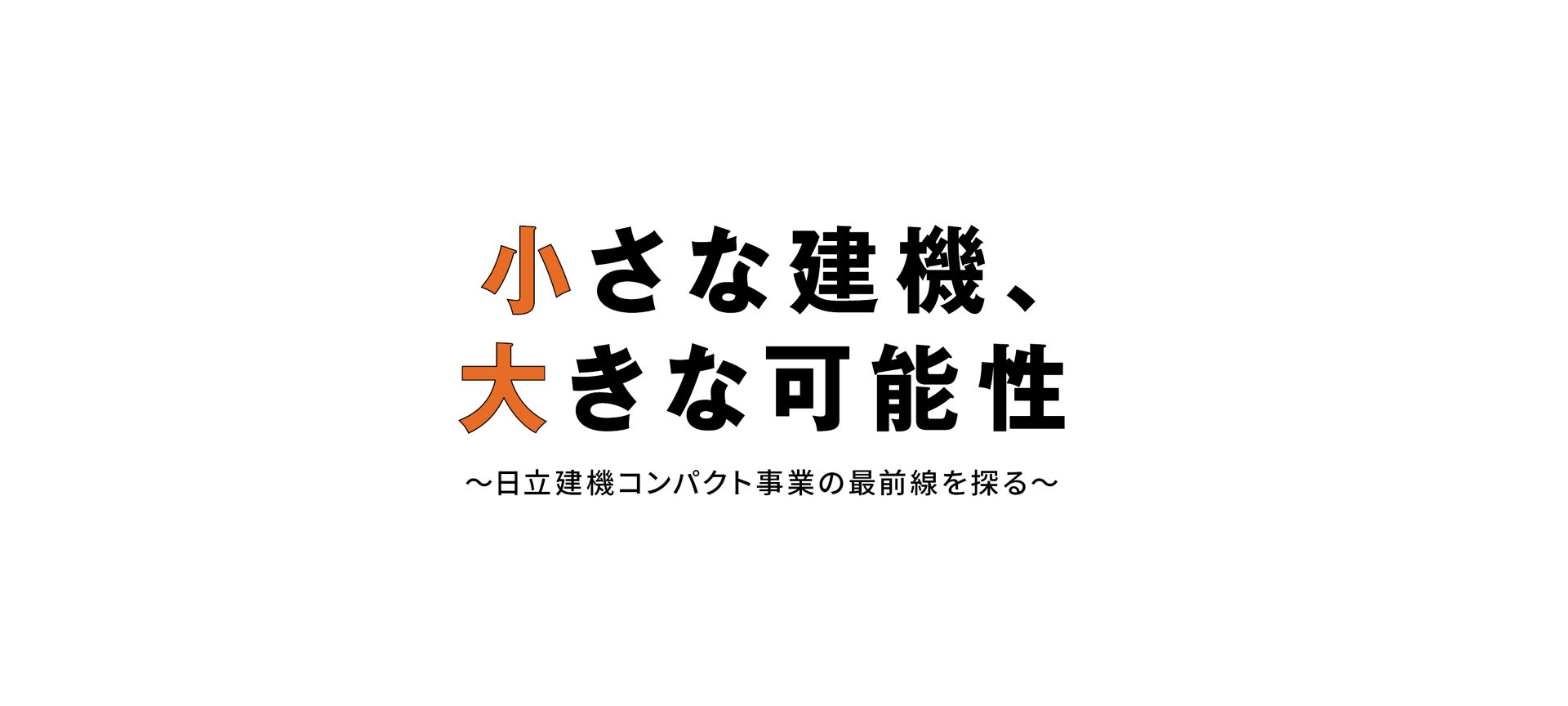



――日立建機グループにおけるコンパクト事業の位置付けと、日立建機ティエラの役割を教えてください。
ミニショベルなどコンパクト製品の需要は2010年代から伸びてきました。2020年代もマーケットは拡大しています。日立建機では2022年に組織をビジネスユニット(BU)制に移行しましたが、市場環境を踏まえてコンパクト事業もBUになりました。コンストラクションやマイニングとともに、日立建機グループの成長・発展を支える柱として期待されています。
BU制は開発から生産・販売まで一貫した組織体制なのですが、日立建機ティエラにはすでにそうした一貫体制が整っていましたから、当社がそのままコンパクトBUになったという形です。ただ、それだけでは他の部門との連携が難しい。そこで日立建機本社内に事業戦略部を設置しました。これにより、他部門との連携強化が図れるようになっています。
――コンパクト製品のマーケット動向についてどう見ていますか。
コロナ禍が収まるころに、世界中でユーザーや販売店からの需要が急増しました。当社はそれに対応できる生産能力が不足していたため、生産設備の更新・再編を行い、従前と比較して3割程度、生産能力が上がりました。
コンパクト製品の主戦場は日米欧ですが、新興国でも都市化の影響があって需要が伸びています。しかしながらインドなどアジア圏では中国メーカーが進出してきているので、それに対抗する戦略も必要になっています。
――中国メーカーは価格勝負だと思いますが、世界で戦う機能や品質の高さが重要になりますね。
コンパクト製品では、サイズは小さくとも中型製品と同じ機能が求められ、小さな空間にその機能を収めなければなりません。開発・設計から製造・組立まで、高いレベルでの製品づくりが求められます。そのために量産ラインではIoTやロボットの活用が不可欠ですし、現場から上がってくるアイデアは積極的に取り入れるようにしています。それが生産性や品質の向上にもつながっていると考えています。
開発試験場を近隣地に移転し拡張したのも、安全性の確認や評価だけでなく、製品開発や品質の確保などの面でも大きく貢献すると見込んだためです。
――日立建機ティエラは電動建機にも力を入れています。今後の開発・販売戦略についてお聞かせください。
最近では5tクラスのバッテリー駆動式ショベルZX55U-6EBを開発、2024年から欧州を中心に販売を開始しました。今後はさらなるラインアップの拡充が必要になってくるでしょう。
日本でも電動建機への注目度が高まっています。「関心」から購買も含めた「行動」に移ってきました。実際にZX55U-6EBと可搬式充電設備のセットで、国内での販売実績も出ています。国土交通省の「GX建設機械認定制度」の認定も取得していますので、国内販売にも力を入れていきたいですね。

――日立建機のコンパクト事業と日立建機ティエラが描く未来や、今後の課題についてお話しいただけますか。
日立建機ティエラのルーツは熊本ですが、滋賀工場ができてすでに半世紀。その長い年月の間に、地元・甲賀市とは深く親密な関係を築いてきました。私たちはメーカーですから、安心・安全な製品をつくってお客さまから選ばれないといけませんし、生産活動も重要ですが、それだけではなくて、地域社会から信頼される会社でありたいですね。
一方、コンパクト事業ですが、やはり成長のカギとなるのは、さらなるグローバル化だと考えています。日米欧だけでなく、特に今後需要拡大が期待できるインドは注視すべきエリアです。
生産効率を上げつつも、高品質な製品を今後もつくっていきたい。めざすはコンパクト製品の世界シェア2桁です。

日立建機ティエラ代表取締役社長
一村 和弘
山口県出身。1988年入社、日立建機土浦工場中型ショベル設計部ホイールショベルグループに勤務。その後事業統括本部建設システム事業部や営業統括本部インド事業部、研究・開発本部コンストラクション事業部などを経て、2022年より現職。
文/斉藤 俊明 写真/小島 真也